発達障害の「注意欠如・多動症(ADHD)」について調べました。
ADHDが疑われる子どもの特徴と、どのような対応が必要なのかご紹介します。
注意欠如・多動症(ADHD)とは?
発達障害の中のADHDは、不注意や多動が特徴です。
そもそも発達障害とは、持ってうまれた能力に極端な凹凸があることを言います。

ADHDの特徴である『注意・欠如』や『多動・衝動』の比率は人によって異なり、成長過程で目立たなくなることもあります。
ADHDは小学生になってから発覚することが多いです。
幼少期に「落ち着きがなく、活発すぎる」ということで、心配になるお母さんもいますが、そもそも活動的な3~4歳くらいまでの子どもは、正常な発達過程なのかどうか専門家でも判断は難しいとされています。
もしかして…発達障害かも? ADHDをもつ子どもの特徴
ADHDの『注意欠如』という症状は、学校ではさまざまな問題を引き起こします。
まず、忘れ物の多さです。
ADHDの場合は、忘れ物の多さを指摘されても治すことができません。
鉛筆や消しゴムなどの文房具を忘れることは、誰にでも経験あると思いますが、ADHDの『注意欠如』は、ランドセルを忘れていくこともあります。
ランドセルは忘れずに持って行ったと思ったら、中身が入っていなかったという例も…。

ADHDの子どもは、声を掛けられると、それまでの作業をすべて忘れてしまうこともあり、授業中は上の空になってしまうこともよくあります。
また、ADHDの子どもは、物事に優先順位がつけられず、段取りも得意ではありません。
そのために、作業も中途半端になってしまいがちです。また、予定の時間に間に合わないということもよくあります。
(物事を先延ばしにするために、宿題をやることもできません)
さらに、大事な物と不要なものを区別ができないために、学校では机の中の整理ができず、家では部屋が散らかっています。
しかしながら、気配り名人で、困っている人がいれば、誰よりも早く気づいて対応できます。
ADHDの子どもに対して、親の対応は?
物が散乱して片付かない子ども部屋をみて、つい注意したくなる親ですが、もう何度目? と、悲痛な思いに駆られることや、なかなか宿題にとりかからない子どもにイライラすることありませんか?
朝は、登校時間ぎりぎりまで、支度以外のことをするので心配にもなりますよね。
しかし、様々な事情で気持ちが沈んでいるときに、飛び切りの笑顔で声を投げかけてくれる我が子は大切な存在です。
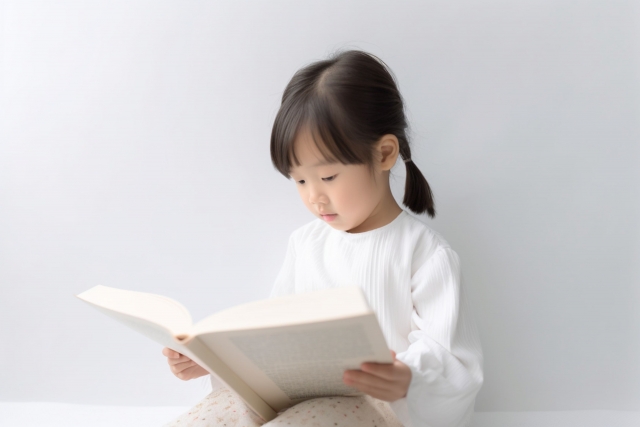
さて、ADHDの特徴を持つ子どもに対して、親はどのように接したらいいのでしょうか。
- 対応のコツ 一度に提示する数を減らす
ADHDの子どもは、身体も気持ちもさまざまな刺激に反応します。
しかし、同時に複数の刺激を処理することが苦手なので、一度に提示する数を減らすことが原則です。子どもの自主性を尊重するのも大切ですが、明確に教えることが必要な場面もあります。
ケガや命にかかわるような危険なことは、一貫性をもち、しっかりと止めてあげましょう。
- 対応のコツ 実年齢ではなく、その子どもに合わせた環境の設定をする
成長過程でADHDの症状は改善する(目立たなくなる)課題もあります。
ゆっくりなだけで、少しずつ成長していきます。
実年齢ではなく、その子どもが、何に困っているのかを把握したら、その子にあった対応方法や環境の設定を工夫する必要があります。
耳からの情報だけでは理解できない子や、話し手に注意を向けることが苦手な子もいるため視覚的な情報の提示や、分かりやすい表現で伝えることが大切です。

遠くから大きな声で注意しないでください。
その子の近くで、小さな声でゆっくりはっきりと伝えましょう。
そして、理解不十分のまま返事をする子もいるため、理解を確認する必要もあります。
自分の気持ちを言葉ではなく、不安な表情、イライラした態度、粗暴な行動、落ち込みの雰囲気などで表現してしまうことも多いADHDの子どもの困りごとを把握するは、周囲が本人の気持ちを推し量る必要もあるといえるでしょう。
- 対応のコツ ストレスがたまる前にリラックスする
ADHDの子ども本人も、ストレスを抱えた毎日を過ごしていると思いますが、そばでお世話するお母さんも大変です。
イライラして大切な我が子を傷つけてしまう前に気分転換で、ストレス発散しましょう。
相手を大切にすることにもつながるので、自分を大切にしてください。

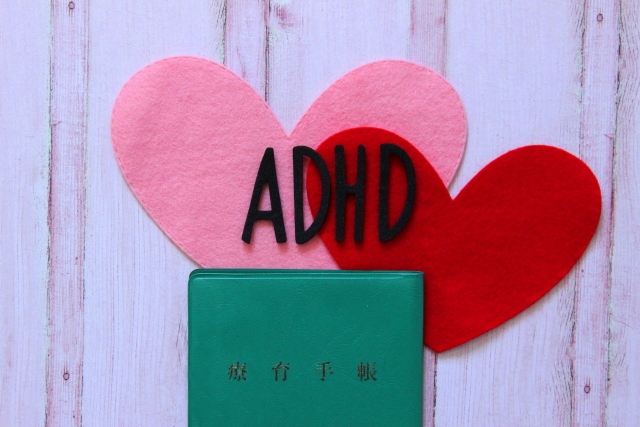

コメント